第2回講義の補足記事です。
明治以降の日本の建築は、おおきくふたつの潮流があると考えられます。
ひとつは大工、棟梁を主体とした建築の流れです。大きな枠組みとしては律令制の時代の中で、領主や一家の主などが権限を持つ社会における身分、階級による建物の仕様に基づき建築されてきました。そして、実際の設計や工事は大工や棟梁を主体として建築されてきたと考えられます。現在ではその流れは主に木造住宅建築の世界で工務店を主体とした建築の流れの中に見受けられます。そのために、設計というものに対しての理解が深まらないという側面も否めないといえます。
もうひとつが、明治以降の設計者の登場による建築設計の潮流です。工部大学校(現在の東京大学)に英国から招聘されたジョサイア・コンドルより建築を学んだ辰野金吾、片山東熊、曽禰 達蔵(そね たつぞう)などのほか、ドイツで建築を学んだ妻木頼黄といった日本人の設計者の登場による近代建築の系譜がはじまります。
また、近代建築の三大巨匠であるル・コルビュジェの弟子である坂倉準三、前川國男、吉阪隆正や、同じく三大巨匠のフランク・ロイド・ライトの弟子であるアントニン・レーモントの系譜にて吉村順三といった日本人の建築家が次々と活躍の場を広げていきました。
このような大きく2つの潮流の中で日本の建築の世界は広く世界にも認知され、多くの世界的なネームバリューを持つ建築家を輩出しています。
ちなみに建築のノーベル賞といわれるプリッカー賞は現在下記の6名の方が受賞されています。
丹下健三
槇文彦
安藤忠雄
伊東豊雄
SANNA(妹島和世+西沢立衛)
坂茂
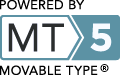
コメントする