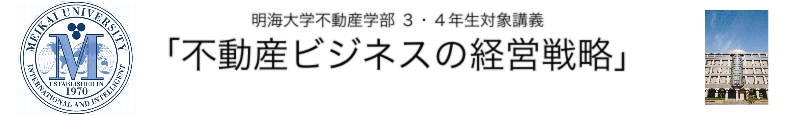2012年11月15日
今週の講師 日本土地家屋調査士会連合会 加賀谷 朋彦 氏
最優秀レポート
【問題1】 講義内容を簡潔にまとめなさい。
一つ目は、土地家屋調査士の業務内容で、それは不動産登記法の目的を達成するために、表示の登記、境界の測量、調査を中心にしている。なお、権利の登記については司法書士が行っている。
二つ目は、筆界と所有権界で、筆界とは、地租改正時に国家が定めた境界であり、筆界の確認をするということも土地家屋調査士の業務内容となっている。所有権界とは、裁判、調停や、合意により発生する境界である。正式な境界は筆界である。
三つ目は、土地家屋調査士が業務を行うにおいて、実際に起きる事で、測量・調査を行うと、よく隣人とのトラブルが起きることがあり、トラブルを防止するために様々な努力が必要となる。
【問題2】本日の講演内容に関して自分の意見・考えを述べなさい。
私が興味を持った講義内容は、土地家屋調査士の業務の範囲です。土地家屋調査士は、登記を行う際には表題部、権利部は司法書士が行うというのは、業務を行う上では効率が少々良くない気がしました。事務所を設ける際に、司法書士の資格も取得をし、司法書士事務所も併設する手もあると思いますが、土地家屋調査士の業務範囲の中に、権利部の登記も入れるという事ができるように工夫をする必要もあるのではないかと思いました。
講演終了後の質疑応答の内容
Q1.土地家屋調査士と測量士との違いは何ですか?
A1.測量士は測量法に基づいて業務を行います。公共測量をします。調査士は公共測量ではなく、登記を前提とするものを行います。双方は、基本的な点はかなり似ていて、使用する機材やそれらの使い方なども同じです。例えば道路を造るとしますね。その際、基準点測量は測量士がやりますが、登記もからんできますから、調査士の仕事ともいえるところがある訳です。オーバーラップしている部分、グレーゾーンの部分があります。その点は、司法書士と行政書士の業務などにも生じています。
Q2.表題登記にADRがあったことが記入されるとのことですが、過去に紛争があったことが分かってしまうと困る事があるのではないでしょうか?
A2.過去に筆界特定をやった記録が残るということです。これは、紛争そのものを意味するものではありませんが、潜在的な紛争がある可能性を示唆するものです。ただし、逆に考えれば、ADRでしっかりとした筆界がある、と考えることもできます。
Q3.現在、土地家屋調査士の数は1万7,000名とのことですが、少ないのではないでしょうか?
A3.土地家屋調査士の数は、10年前は1万8,600名ほどでしたから、1,400名ほど減っています。逆に、弁護士や司法書士の数は増えています。ですから、調査士の数が少ないか、というと、私の個人的な考えでは、まだ少し多いのでは、と思っています。つまり、平成8年と比較して、現在のマンション数は60%減っています.業務が減っているということです。土地家屋調査士は、これから業務の拡大が必要となってくると思います。例えば、中古住宅流通市場を拡大する動きがありますが、その際に必要となる住宅履歴情報などは、地盤情報等を把握している調査士が行うようにするなどが考えられるでしょう。
Q4.境界確定でもめるということですが、業務を円滑に進めるにはどのような点に注意する必要がありますか?
A4.やはり若いうちは、なかなかうまく行かない事が多いです。年を重ね、経験を積むことでしょうね。きちんとした資料収集をした上で、自信を持って、冷静に対処する、ということでしょうか。
私も、立ち会いの前は、今でも不安です。悪い人ばかりではないけれど、急に怒鳴り出す人もいたりします。ちょっとしたずれが紛争を拡大してしまいます。境界紛争は人格紛争といいますが、人の感情の行き違いを解決してあげると、境界確定の方もうまくいったりしますね。
Q5.土地家屋調査士の職業倫理は、どのようなものでしょうか?
A5.連合会倫理規定があり、話すと長いのでお話ししませんが、日々研鑽、ということでしょうか。
Q6.どのようなところにやりがいを感じますか?
A6.私の個人的な感覚ですが、申請代理は機械的に手順を踏んで行うので、それよりも、土地の境界問題でうまく解決できて、境界が決まるとうれしいですね。その過程で、アドバイスをしたり、客観的資料を収集したり、解決に向けた業務にやりがいを感じます。
質問表への回答
・境界杭はなぜさまざまな形状があるのか、という質問がありました。問い合わせ中ですので少々お待ちください。
・どのような人が土地家屋調査士に向いているのか、という質問がありました。これも問い合わせ中です。